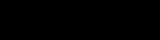日本が高度成長期だった頃の競艇を知る、ゲストの方からコラムを寄せて頂きましたので、
掲載させていただきます。当時の活気に触れられたような気がします。ありがとうございました。
競艇の思いで
初めて競艇を楽しんだのは、昭和33年、先輩に誘われての常滑競艇であった。印象としては、スピード、モーター音などの迫力に圧倒された。
当時は2連単と2連複だけである。それに、出走表とて年齢、ランク、出身地、過去の実績程度の紹介のみで予想紙などはない。舟券売り場の窓口が、2連単が30、2連複が15、の計45ヵ所ある。窓口には人の手首が入る穴が空いて、中に女性職員がいる。売り場だけでも計45名の職員がいることになる。
オッズ表などはない。まだソロバンの時代である。舟券を買う時は、客が混んでいる売り場の人数を見て配当額を予想する、例えば、1-4の売り場が混んでいたら500円位とか、客の並んでいる人数で予想する。舟券購入の際も、今のような投票カードなどない、窓口の穴にお金を持って手を入れ、手に舟券が渡されるまで手を抜かないのである。
千円札で釣銭を受け取るような買い方は出来ない。千円以下の購入は両替して置かなければならない。300円を入れると100円券が3枚、500円だと5枚が手の平に渡される。特券もあり、1枚が200円であった。口頭で『特券で』と告げる。
1ヵ所で、3の1着流しとかは買えない。買うとすれば、5ヵ所の売り場を回ることになる。前売りを買うにしても、レース毎に異なる組み合わせを買うことは出来ない、例えば1-4の全レースこれは可能である。
売り場の外には予想屋と呼ばれる者が7~8人いて、1メートルほどの台上で、レース展開を自信ありげに、ダミ声で客を呼び込んでいる。たしか30円だと記憶しているが、本命か穴か、どちらかを彼らに告げて渡すと、小さい紙にレース予想を4点ほど早書きして渡してくれる。当然、的中率の高い予想屋には客が集まる。予想した穴が、的中しようものなら大変だ。大きな紙に赤色で何重にも丸印を付け、これ見よ、とばかりに大威張りである。客も御祝儀を予想屋にあげて共に喜んでいる。
舟券売り場の裏には、オデン屋、食堂などが並んでいる。勿論酒類もある。自家用車の少ない時代である。ほとんどの者がビールや、酒を飲みながらの観戦であった。食堂で飲み食いしている者は、常滑特有の3周目の鐘が鳴ると、舟券を握り締め、スピーカーのレース状況に耳をかたむける。レース映像などはない。観覧席の人達は着順が決定すると、握っていた、つかの間の夢を一斉に投げ捨て、紙吹雪となって舞い上がる。
先輩達も全員やられたのだろう、『あの野郎の妨害がなければ』、『転覆しなかったら』と、たら、れば、の連発が止まらない。いつもの事だが機嫌の悪い荒れた帰り道となる。自分は初心者なので、素直に本命買いをした。成果としては、飲み食い分が浮いていた。
常滑は、常夏とも言われる暖かい所だが、晩秋から冬季にかけて、浜風に身を震わせての観戦だ。今は青森でも風雨の心配もなく、冷暖房の完備された屋内で鮮明な映像で全国のレース場の実況が楽しめる。いかに文化の進歩とは言え、ボートピアとは有り難い。
当時サラリーマンの月給が1万3000円ほどの時代の事である。
競艇ファンより